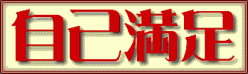1日目の観戦は様子見。
2日目の京都ステージが観戦本番。
2日前にコースを自転車で走り、プロの体力が桁外れであることは分かった。
素人のおっちゃんだと約45分。プロはこれを25分ほどで周回するらしい。
目の前を選手が通り過ぎたら、周ってくるまで何もしないのはもったいない。
セレモニーランを見送ったら、KOM後の下りに入ったすぐのヘアピンカーブまで登る。
「KOM」とは、「King of Mountain」つまり、山の王様。日本語で言うと「山岳賞」
ここを一番で通ると、山岳ポイントが獲得できる。詳しくは弱虫ペダル等で勉強しよう!
選手が周回してくるまでに、その観戦ポイントまで逆周りで脇道の坂を登る。
選手よりも先にたどり着けるのか?選手が走る距離の1/3しかないが、こっちは一人。更に素人だ。
と、心配していたが、スタートが5分遅れになったことも有り、余裕でポイントに到着。
まだほとんど人はおらず、最前のベストポジションで観戦。
ギリギリのスピードで下っていくかと思ったが、まだ1周目。そんなに無茶な速度ではなかった模様。
でも、集団で1台、後輪が横に滑っていたので、決して遅い速度ではない。
最終周回でのこのポイントを見てみたいが、ゴールのほぼ反対に位置する。諦めよう。
選手が来る5分前に、赤色の旗を2本立てた車がやって来る。
それ移行は、コース内の移動禁止だ。
その後、パトカーを含む色々な車の後、選手が通過、最終選手と救護車などが通りすぎて、最後に緑色の旗を立てた車がやって来る。
その後は、移動OK。
前日、この移動時に、自転車から降りて徒歩しか認められなかったら、相当過酷な観戦だなと思っていたが、殆どの区間で自転車での移動が認められていた。
1周目を見送った後は、KOMへ移動。
見渡しがないため、選手がいつ来るのか、見た目では分からないが、遠くから歓声が近づいてくる。
ビデオ撮影しながら、カメラで写真撮りながら、目にも焼き付けながら。
Abema Freshなるインターネットライブ放送を聞きながら、スマココという位置情報が分かるアプリを見ながら観戦したが、予習が甘く、先頭と集団の時間差くらいしか頭に入ってこない。
自転車地図アプリのWAHOO用iPhone1台と、ライブ放送視聴用nexus5の2台も駆使したが、ちょっと欲張り過ぎて消化不良。みなさんは純粋に応援しましょう。
コース上の観戦者が乗る自転車は感覚的に、8割がロードバイクで、1割が折りたたみできる感じのコンパクトバイク、あとの1割がマウンテンバイクとママチャリ。
因みに年齢層は高め。平日に高価なバイクで観戦に来ることができる層は、推測したそのままズバリ。
3周目の観戦ポイントは、KOMまでの登り。
くねくねとしたコースを見下ろせる側道から座って観戦。
ちょっと太陽も見えて、Tシャツ一枚でちょうど。
4周目は登りの中にある下り区間。
ちょうど下ってくる選手を正面から見える場所。
速度が相当出ていて、単車や車も100kmぐらい出てるんじゃないかと思う速度で通り過ぎていく。
自転車の集団が横を抜けて行く速度感は、感動ものである。
因みに普通のおっちゃんの試走時は50km/hちょい。プロの集団だと70km/hくらい出てるのか?
5周目は登りS字。
いかにもな山間の登りで、崖下には小川が流れている。
5周目なのに登っていく。ダンシングもあり。
普通のおっちゃんだと一番軽いギアで地道に10km/h前後で登るしかない。
6周目は、フィニッシュ地点あとにある補給ステーション。
速度が速すぎるなかのボルトの手渡しは、腕が抜けそうだ。
取れなくてボルトが飛んで行くシーンもある。
そういえば選手が空のボルトを放り投げていた。
あれ、拾ったらもらえるのかな?
取れなかった選手のためにチーム間、敵同士でもボトルを分け与える事は珍しく無いらしい。
そしてゴール。
フィニッシュラインは人だらけで、全く場所がない。
このコースは、4車線の片側2車線のみを通行止めしているため、観戦は片側からのみ。
通常の観戦より片側に倍の観客がいることになる。
ちょっと手前の2列目に陣取って手を伸ばして撮影。
フィニッシュは全く見えなかったが、ゴールスプリントは凄まじかった。
表彰式。
算数が苦手な主催者がポイント計算に苦戦し、30分ほどステージ前で気をつけ!
いや、頑張ってもらってるので、こちらも頑張って立ちます。2時間でも3時間でも。
おめでとう!優勝者!
おめでとう!いろんな受賞者!
来年は、もうちょっと選手を予習しておきます。
結論:観戦は一人でも十分楽しい!でも、何人かですれば、もっと楽しそう。